|
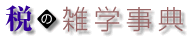
第64回
ストック・オプション課税裁判の傍聴から
現在東京地裁で進められているストック・オプション課税裁判を傍聴してきました。「給与所得」か「一時所得」かという問題、給与所得の要件としての「対価性」の問題、課税上取扱いが変わったとする「信義則」の問題などの争点について争っています。原告の一人が争点とは離れて、面白い陳述をしていました。その方は、現在ベンチャ−キャピタルファンドの普及の仕事をしていますが、次のように述べられています。「ストック・オプションにより受けた経済的利益は、国に税金として差し出すばかりではなく、新たな事業を起こそうとする人たちへの投資として活用したい。所得の再分配を国に依存するのではなく、民から民への投資を普及させるためには、民に資金を残しておくことを考えるべきだ。民から民への投資のほうが、専門性を持った効率的な投資を行うことができるはずだ。そういった税制を作り上げることが求められているのではないだろうか。」
その方の主張は、必ずしも訴訟と直接関係があるとは思えません。ストック・オプションは、所得の問題であり、どのようにその所得を使うということとは、別次元の問題だからです。しかし、税制のあり方という面では、含蓄のある意義深いものと感じられました。
現在進められている税制改革は『広く薄く』の観点から方向性が示されています。『広く薄く』の課税のあり方というのは、課税ベ−スを拡大し、累進構造を緩和するということです。これまで一部の富裕(高額所得)者に対して課税が偏っていたのに対して、国民全体で税金を負担することになります。見方を変えれば、『金持ち優遇』の批判が生じることになります。
さらに、現在の税制改革の根底には、『政府不信』の声が充満しています。政府税調の『税についての対話集会』においても、財政支出のあり方に対して不満の声が噴出していました。いわゆる富裕者の側からも、現在の国家による富の再分配が非効率ではないかとの疑問が提起されています。民から国に対して税金として取り上げて、財政支出として分配するよりも、民から民に対して効率的な支出を行うことを求めているのです。ベンチャ−ビジネスへの直接投資に優遇税制を設けたり、寄附金課税・NPO法人に対する課税を優遇することも民から民への効率的な支出を求める声に対応するものとなっています。
民から民への資本の移転(投資・寄付)を充実させるには、国民の精神的な自立が欠かせません。『金持ち優遇』税制の恩恵を受ける富裕者が、私財の蓄積に走るようなことことでであれば、国家経済も国家財政も根底から崩壊してしまいます。『金は天下の回りもの』という意識を国民全体が共有し、自立心をもって経済活動を行わうことができなければ、国家により強制的に循環させるより、経済を運営させていく方法が見当たらないことになります。
政府の財政支出のあり方を批判する声が多いということは、政府に代わって国民一人一人が適切な消費・投資行動をすることが求められるということです。真の税制改革・財政改革には、国民一人一人の自立が不可欠といわざるをえません。
バックナンバー
(2002.7.5 ビジネスメールUP!
311号より
)
|

