|
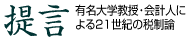
第9回
道路特定財源税を環境税に!
筑波大学大学院教授 品川芳宣
小泉内閣は、“構造改革”の年始めとして、道路特定財源を一般財源化するという。案の定、野党ならぬ与党自民党のいわゆる族議員が猛反発している。その族議員の代表格日く、「道路が要らないというのであれば、ガソリン税等は減税、廃止すればよい」とのことである。
ところで、道路特定財源税は、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び自動車重量税からなっており、それらの税収は、総額5兆8,000億円にものぼるという。また、自動車所有者に対しては、地方税として、自動車取得税、自動車税、軽油引取税等が課せられる。
その中でも、揮発油税だけで、ガソリン1リットルに約50円(販売代金約60%)も負担させられることもあって、“車は税金で走っているようなもの”と言われるのも無理からぬところがある。
しかしながら、このような税負担は、我国特定のものとも言い難い。確かに、アメリカに比較すると、ガソリンに対する税負担は我国の約15%に過ぎないが、ヨーロッパ諸国では、軒並我国よりも高い税負担を課している。そして、ヨーロッパ諸国では、一部の国でCO2の排出量に応じて重課するという環境税を導入しており、環境税と銘打っていない国でも、いずれも環境税への衣替えを狙っているようにも見られる。もちろん、それらの石油関係諸税は、一般財源としてである。
我国においても、かかる地球規模的な問題に取り組まなければならないことは当然であるが、東京都知事が主張しているような排気ガスに対する公害対策も緊急な課題である。
然すれば、石油関係諸税は、今後一層重課せざるを得ないのであって、道路との結び付きがなくなっても、減税する余地はないものと考えられる。
いずれにしても、この機会に、揮発油税等の石油関係諸税については、道路特定財源税から脱皮し、環境税としての機能を重視した税制に衣替えする必要がある。そして、CO2の発散量に対応した税率構造に変えて行けば、軽油使用車等からこれみよがしに吐き出される排気ガスとも無縁となり、まさに一石二鳥が期待できる。
なお、道路特定財源の一般財源化に伴う結果的な地方の財源縮減については、別途検討すべき課題である。
バックナンバー
(2001.6.22 ビジネスメールUP!
168号より
)
|

