|
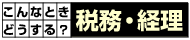
平川税務会計事務所 須長 孝行
第62回
法定準備金の減少手続き
☆ 利益準備金の積立限度額に関する改正
積み立てるべき利益準備金の金額は、改正前の商法の規定によれば、利益準備金単独で資本金の4分の1に達するまで、利益処分する金額の10分の1以上、中間配当額の10分の1として義務づけられていました。
これに対し、改正後の規定では、資本準備金と利益準備金を併せて資本金の4分の1までとなりました(商法288条)。
☆ 法定準備金減少手続きの創設
昨年の商法改正の1つに、法定準備金の減少手続きの創設があります。改正前の法定準備金について、欠損填補または資本組入れを行う以外に、その取り崩しが認められていませんでしたが、株主総会の決議をもって資本準備金及び利益準備金の合計額より資本金の4分の1に相当する額を控除した額を限度として、資本準備金及び利益準備金の取り崩しを行うことが出来るようになりました(商法289条2項)。
つまり、欠損填補または資本組入れにしかその使用が認められていなかった法定準備金について、株主総会の決議および債権者保護の手続きを充足することを条件として、取り崩しの上配当可能利益に充当することが認められました。
また、法定準備金の取り崩し順序についても、従来欠損填補の場合、利益準備金、資本準備金の順に充当しなければなりませんでしたが、改正後はどちらを先に取り崩しても構わないと解されています。
☆ 取り崩しの効力
法定準備金減少の効力は、株主総会の決議が行われた日ではなく、債権者保護手続きをはじめ全ての手続きが終了した時点で発生します。
従って、取り崩し原資を配当にまわす場合、株主総会において法定準備金の減少決議を行い、承認されたとしても同じ株主総会における利益処分でその取り崩し原資における配当を行うことはできないことになります。
☆ 留意事項
法定準備金の減少手続きは、資本減少の手続きにならったものですが、資本減少のように特別決議は要件とされておらず、普通決議で足りる取り扱いとなります。
しかし、株主総会の承認を受けて行われる債権者保護手続きに関しては、資本減少の手続きを準用する取り扱いとしており催告手続きが必要となります。
この法定準備金の減少手続きに異議を述べる債権者がいる場合には会社は個別に弁済しなければなりません。
従って、法定準備金の減少手続きについては、それが自己株式の取得に充当するためであれ、配当可能財源に充当するのであれ、その効力が発生してからでないと、実際の行為が行えない為、債権者保護手続との関係でその効力発生時期が重要となります。
(2002.7.22 ビジネスメールUP!
318号より
)
|

