|
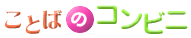
確定決算主義の2つの方向性(その1)
法人税の所得計算には、確定決算主義が採用され、商法に規定する株主総会で承認された決算をもとに、税務申告を行うことになります。
この確定決算主義が、改革・保守の両面から、その存在意義が問われています。
どのような問題点が指摘されているのか、まず、改革面から取り上げてみましょう。
連結納税制度が導入されると、経済的一体性を有する企業グル−プ(複数の企業)が、申告・納税の主体になります。商法は、原則的に個別企業における利害関係者(債権者・株主・経営者等)間の調整を規律するものであり、企業グル−プを対象とするものではありません。証券取引法や企業会計の影響から連結重視の方針をとるといっても、企業会計上の連結グル−プの範囲と法人税法上の連結グル−プの範囲が異なっているので、商法・企業会計に基づく決算と法人税法上の連結所得との距離がかい離してしまうことになります。
具体的には、事業年度と損金経理要件の問題が指摘されます。企業グル−プは、それぞれ、固有の事業年度(会計期間)を有していますが、連結納税制度では、連結親法人の事業年度に合わせています。連結親法人と事業年度が異なる連結子法人は、連結納税のための決算(?)を承認する株主総会等を開催することは、商法上想定されていません。
連結親法人と事業年度が異なる連結子法人は、自社の株主総会で承認を受けていない会計処理を連結所得の計算に取り込まれることになりますが、減価償却費の計上など損金経理を法人税法上の要件としているものとの整合性に無理が見られます。
国際会計基準の導入・連結納税制度の導入などで、法人税法も改革を余儀なくされていますが、制度設計上、企業会計と税法を密接にリンクしつづけていくこと(確定決算主義を維持していくこと)が困難になっているのです。
(2002.9.9 ビジネスメールUP!
336号より
)
|

